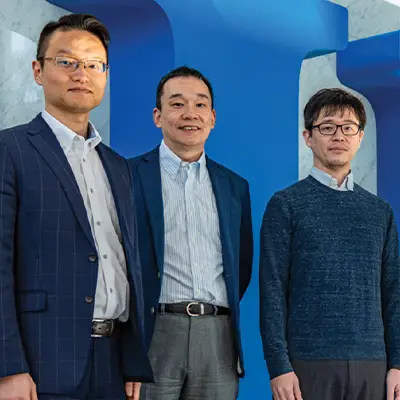A*STAR傘下のISCE2とのジョイントセンター設立でAPACの研究開発拠点としての機能を強化
カーボンフリーの次世代燃料として注目を集めるアンモニアに関するノウハウを筆頭に、世界から注目を集めるIHIの環境技術。IHIは造船業を祖業とし、現在では航空エンジンを主力事業に、「資源・エネルギー・環境」「社会基盤・海洋」「産業システム・汎用機械」「航空・宇宙・防衛」の4分野で世界に向け事業を展開している。そんなコングロマリットが環境技術の開発に注力するのは、それらのどの事業においてもCO₂排出削減が避けられない課題だからだ。
その取り組みは、 “2050年までにバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを実現する”と宣言をするほどだが、IHIがアジア太平洋地域の研究開発拠点としてシンガポールを選んだのはなぜなのか。小林氏はその利点を解説する。
「シンガポールは小さい国ということもあり、国際的な才能にオープンです。シンガポールの公的部門の研究開発機関であるシンガポール科学技術研究庁(A*STAR)にも多彩な研究者が世界各国から集まり、非常にグローバルな研究が行われています。そこにベンチャー企業などが加わって形成されたエコシステムに我々も加わり、イノベーションを促進したいと考えました」
この開発において、同社がシンガポールの政府機関や企業と連携するというニュースが2022年、相次いだのである。
まずは3月。A*STAR傘下の化学・エネルギー環境持続可能性研究所(ISCE2)と、共同で研究開発を行うジョイントセンターを設立するためのMoU(基本合意書)に調印した。研究の主な対象は温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルのソリューションで、小林氏は経緯をこう語る。
「2014年1月にA*STARと包括的研究開発契約(Master Research Collaboration Agreement)を締結し、化学技術を始めとしたさまざまな技術分野で効率的な研究開発を実施するために連携を始めました。A*STARとはCO₂から天然ガスの主成分であるメタンを製造するメタネーション技術に関して、『包括的研究開発契約』を締結する前の2011年の合意から2018年まで、共同で研究していました。2019年にはデモ装置も完成させ、その成果がきっかけとなり、今回の運びとなりました」
また小林氏は、A*STARと協力するようになった理由について続ける。「IHIは2000年代後半から循環型社会実現に向けて取り組みを始め、日本では横浜の研究所で開発を行ってきました。しかし、国内の活動だけでは日本向けのソリューションは生み出せても、国外の需要に合わせられない。世界に向けた開発をするために、アメリカ、イギリス、中国、そしてアジア太平洋地域ではシンガポールに研究拠点を置き、A*STARと協力するようになったのです」
世界が注目するアンモニア技術の開発でシンガポール企業と連携
さらに2022年10月には、同社のカーボンニュートラル技術のなかでもとりわけ進展が目覚ましい燃料アンモニアの利用について、シンガポールに拠点を置く、アジアを代表する再生可能エネルギー関連企業・SembcorpとのMoU調印が発表された。
燃料アンモニアの利用とは、燃焼してもCO₂を発生しないアンモニアを火力発電などに用いることだ。IHIは、この技術の開発からアンモニア供給網の整備まで、サプライチェーン全体の構築に急ピッチで取り組んできており、今回の合意について小林氏はこう説明する。
「東南アジアのエネルギーおよび化学産業のハブであるシンガポール・ジュロン島のSembcorpのエネルギーインフラ設備などに、アンモニア利活用技術を導入することの可能性を両社で議論しているところです」 発電用の燃料アンモニアは、ガス処理設備などの既存のインフラを大きく改造することなく、火力発電に利用することが可能だ。そのためコスト面などで有利であり、まさに世界的に期待が高まっている。
「Sembcorpの設備があるジュロン島は、東南アジアのエネルギー集約拠点の一つです。そのジュロン島についてシンガポール政府は2021年、持続可能な化学・エネルギー産業拠点へと転換する『サステナブル・ジュロン島』を公表しました。今回の取り組みはこの目標の達成に向けて低炭素燃料活用を推進するもので、日本とシンガポール両国で、同地域の脱炭素化を先導していけるように尽力したいと思っています」(小林氏)