セイコーは世界初のクオーツウオッチを発売し、グランドセイコーなどのブランドで知られる世界的メーカーだ。1881年の創業以来、最先端の技術によって革新的なウオッチを世に送り出してきた。
シンガポールとジョホールバルのシナジーで世界ナンバー1を目指す
セイコーは世界初のクオーツウオッチを発売し、グランドセイコーなどのブランドで知られる世界的メーカーだ。1881年の創業以来、最先端の技術によって革新的なウオッチを世に送り出してきた。

そんなセイコーがグローバル市場に向けた一大製造拠点として位置付けているのがシンガポールであり、その対岸にあるマレーシアのジョホールバルである。同社はこの両国に製造拠点を設けることでさまざまな相乗効果を生み出している。さらに、この二つの製造拠点は新たにスマートファクトリーへと進化を遂げようとしている。今回のケーススタディでは、セイコー・マニュファクチャリング・シンガポールのマネージングダイレクター木原弘之氏とゼネラルマネージャー武田良彦氏と共に、シンガポールに製造拠点を設立してからの歩みから、課題への対応や機会の獲得に向けてどのような進化を続けてきたのかを紹介します。
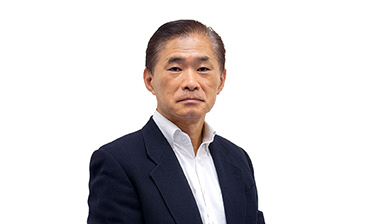
マネージングダイレクター 木原 弘之 氏
二拠点が連携しグローバル市場に展開
セイコーがシンガポールに進出したのは1973年。今からさかのぼること40年以上前に初の海外製造子会社として設立されたのが始まりだ。「セイコーがシンガポールでウオッチの製造を開始したのは1974年、1976年のウッドランズ・ニュータウンの新工場の開所式には、時の首相リー・クアンユー氏にも出席いただきました。当初は、婦人用時計、子供用時計、ストップウオッチのムーブメントの製造を行っており、産業の高度化によって高精度のウオッチが生産されるようになりました。その後、紳士用、婦人用の時計や電子クオーツ時計などムーブメントの生産を行い、やがてシンガポールでは、クオーツウオッチムーブメントも生産し、当初の人員は4倍に増え、2年後の工場拡張で生産量は20倍になりました。」(木原氏)その後生産設備の拡大はシンガポールにとどまらず、1989年から2001年の間には、シンガポールの対岸であるマレーシアのジョホールバルにも製造拠点を設けている。「以来、シンガポールとジョホールバルの工場は、セイコーのグローバル製造拠点の一つとして、中国や香港など世界に出荷を行っています。また、取り扱い製品もストップウオッチからさまざまなムーブメントへと拡大を行い、多種多様のラインナップをこの地域で製造を行っています。」(木原氏)2020年4月にはシンガポールとジョホールバルの生産拠点はセイコーウオッチの下で再編され、この地域で部品生産からムーブメント組立までを一貫して行う体制にて進めている。

ゼネラルマネージャー 武田 良彦 氏
シンガポールとジョホールバルの相乗効果
ジョホールバルへの進出はシンガポール進出の延長線上にある。「ジョホールバルはマレーシアの南部に位置し、セイコーのシンガポール事業に近いため、マレーシアでの事業展開には最適な場所でした。シンガポール工場では、安定した電力供給と汚染がない水の供給があり、より技術的に複雑な生産工程を行っています。また、ジョホールバル工場では、労働集約型の製品を生産しています。セイコーは、両工場の利点を活かして、部品の移動・交換を行っています。また、ここ数年、マレーシアでも自動化設備の導入を進めています。」(武田氏)さらに、この2つの工場の場所が近いということは、セイコーにとって更なるメリットがある。シンガポール工場で培った事業ノウハウと技術力をマレーシアで活かすことができる。シンガポール工場から機械設備を移すだけではなく、技術的な専門知識を指導しやすく、事業成長を素早く波及させることが可能であったためだ。現在でもシンガポール人の技術管理者が現地スタッフの研修を行ったりするアタッチメントプログラムなどがある。当初はサブアッセンブリー工程のために設立されたラーキンの事業所のみであった。その後、テブラウに部品生産のための工場を設立し事業を拡大している。シンガポールとジョホールバルのオペレーションの緊密な連携は、セイコーにとって大きなメリットとなっている。
パンデミック時にも強い2工場の相互運用性
2つの生産拠点の関係の強さを示す事例として、新型コロナウィルスのパンデミックの際の影響が挙げられる。多くの国が感染拡大を防止するためにロックダウンを行い輸出入も大きく制限される事態となった。それによって多くの企業が原料や部品の調達ができず、製品の出荷が遅れ、市場ニーズへの対応ができない事態が引き起こされた。しかしシンガポールとジョホールバルとの間でのサプライチェーンの分断は最小限にとどまることができたという。「セイコーのシンガポール工場とジョホールバル工場では毎日のように出荷が行われています。セイコーはマレーシアの移動規制命令中においてもシンガポール経済開発庁(EDB)の協力を得ることで両国間の輸送にホワイトリスト入りしており、出荷が途切れることなく行われました。また、セイコーは両国間における輸送数を増やすことでオペレーションにバッファーを設け、分断を防ぐことに成功しています。」(武田氏)
コアとなる人材獲得に向けた新体制を確立
セイコーはおよそ40年間にわたって2つの国で事業を展開してきており、これまでの歩みは概ね順調に進んできたが、その過程でいくつかの克服しなければならない課題がある。その一つが人材獲得に関するものだ。現在、ジョホールバル工場では従業員数が1400人を超えているが、そのうちの約4割を占めるのが外国人労働者である。一方、製造技術と経験を持った現地の従業員を採用することが難しくなっている。その理由の一つが、汚い、騒がしい、油っぽいという労働環境や労働集約型の作業に対するイメージである。これはジョホールバルだけではなくシンガポールでもいえる共通の課題で、優れた現地スタッフを雇用するためにはセイコーは新たな取り組みを行っている。一つが新賃金制度の実施である。「ジョホールバルでは、現地の優秀な労働者の獲得が一つの課題です。セイコーでは新たな人材獲得に向けた体制を確立しています。この制度はシンガポールで実施した新制度で、これをジョホールバルの工場でも導入し、現地従業員の取り込みを図っています。この制度は従来のような年功序列ではなく、従業員の能力を重視した賃金制度で『仕事の価値と応用力』をベースに、業績に応じた賞与が支給されます。またコアとなる社員を確保し、職場環境の改善や知識や技術を定着させる取り組みも行っています。」(武田氏)
スマートファクトリーに進化
世界的にインダストリー4.0への導入が加速する中、セイコーも2019年からi4.0の取り組みを行い工場の変革に力を入れている。その取り組みの一つが、スマートインダストリー準備指標による評価だ。スマートインダストリー準備指標とは、製造業がインダストリー4.0を導入する際に、プロセス、テクノロジー、組織の3つの指標で分析を行い、自社がどの程度準備ができているのかを評価するツールだ。EDBが2017年に発表し、2020年には世界経済フォーラムと提携しスマートファクトリーへ移行するための国際標準化が行われた。2019年にこの指標に基づいた評価が行われ、セイコーの重点分野は「垂直統合」と分析された。「セイコーでは、スマートインダストリー準備指標の分析に基づきERP(Enterprise Resource Planning)やMES(Manufacturing Execution Systems)といったITシステムの導入を行い作業効率の向上に取り組んできました。これにより生産工程を紙で管理するのではなく、QRコードで管理するシステム化を進めています。さらにこのQRコードをスマートフォンでスキャンすることで、リアルタイムにサーバーにデータを取り込むことが可能で、データに基づく解析と改善につなげることができます。」(武田氏)また、品質測定の工程でのプロジェクトでは、作業中に品質に問題があると思われる測定値があれば、コンピュータで遠隔でパラメータを調整するだけで、必要な仕様に調整することができる。
セイコーはシンガポールとジョホールバルの二つの拠点の特性を活かし連携させることで、自動化された生産体制の拡大やサプライチェーンの安定性、人材教育に活かしている。シンガポールでベースとなる技術やシステム、制度を確立し、それをジョホールバルと共有するやり方だ。この双方のシナジー効果とデジタル化・自動化によって、シンガポールとジョホールバルの工場は一大製造拠点へと進化し、セイコーの世界ナンバーワンの機械式ムーブメントサプライヤーになるという目標を支えている。